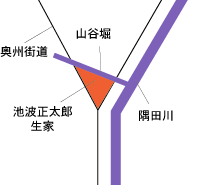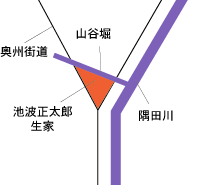-
▼つまり、「大川(隅田川)の西側二つ目」を通る奥州街道をたどるとき、作家の生家がその分岐点となるのだ。「山谷堀をわたり、まっすぐに千住大橋へかかろうという、その道すじの両側に立ちならぶ寺院のすき間すき間に在る町家の一つ」と書くとき、作者は隅田川、奥州街道、山谷堀という三つの線によって生まれた場所を位置づけ、そこから、この小説の舞台へと道をたどっているのだ。▼生まれた場所のすぐそばを通過し、小間物屋への道を彼ならぬ虚無僧姿の十蔵が歩く。(妙だな・・・・・・?)と足をとめる。とめたところから、作者の意識は、生家からの道筋をたどる。十蔵が察知する犯罪の気配に、作者が察知する記憶の気配が織り込まれている。
▼さらに続く下りにも、作家が自らの記憶を察知しているらしい部分がある。材木置場から土の匂いがするところだ。ここには、少年期の作者の材木の香りの記憶が混じっているのではないか。「江戸切絵図散歩」の深川の話に次のようにあるのは偶然ではあるまい。
■
木の香にまじりというのは、いうまでもなく、江戸の材木商の大半があつまっていた場所、すなわち[木場]で、その広大な材木置場や堀川に集積されている膨大な材木の香りは、樹木の生命力を濃厚に感じさせ、少年の私には生臭いほどだった。
(江戸切絵図散歩/池波正太郎/新潮社)
▼そして材木置場からの匂いを確認したところで、作者は十蔵となり、十蔵から虚無僧になる。尺八を鳴らし始める。▼この、十蔵の「妙」な間。寺と寺の間の細道のようなわずかなすき間。テクストが立ち止まり、生家へ帰っていく、春の匂いのようなすき間。尺八を鳴らすとき、最初に洩れる息のようなすき間。それらをたとえば植草甚一にならって「リラックス」と言ってみようか。
■
余談になるけれど「鬼平犯科帳」はもちろん、池波正太郎の「剣客商売」でも「必殺仕掛人」でも、いまの下町にあたる江戸時代の町が事件の重要な背景になっていて、ぼくみたいな時代小説にたいする頓珍漢でも、「江戸名所図絵」をひろげて楽しむことがある。池波ファンとしてそんな気持ちになっているとき、人形町の焦点に明かりがつく夕暮れどきからがいいんだが、たとえば横町の小間物屋のまえを通りすぎたときなど、まあ京都の町にちょっとばかり似たところがあるなと思うのはとにかくとして、ぼくは「鬼平犯科帳」のある場面をふと連想することがある。そうして歩きながら気持ちがリラックスするのだった。
(鬼平犯科帳(一)解説/植草甚一)
▼この、作者の生家から道をたどりはじめた鬼平犯科帳の第一話は、鬼平こと長谷川平蔵が、妻の久栄に子供を引き取る話を持ちかけるところで終わる。「おれも妾腹の上に、母親の顔も知らぬ男ゆえなあ・・・・・・」。生まれた場所から始まった話は、生まれ落ちることを語ることで終わる。つぶやく声が洩れている。声にならぬ、息のようなすきまが、冬の朝の陽ざしのように縁にながれこんでいる。リラックス。
▼とはいえ、読者はなにも池波正太郎の生家がどこかを知る必要はない。浅草のそのあたりがどのような場所か、予備知識が必要なわけでもない。ただ、十蔵が立ち止まるときの「妙」なすき間に敏感であればよい。その敏感さが、川沿いに道を走らせ、堀を渡らせ、道をたどり直させる。そして、鬼平犯科帳の「リラックス」に立ち会える。
|